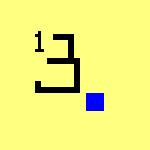朝、5時50分にセットしてあったアラームを止めた記憶が甦る。ニュースでは残忍な犯罪のことが報じられていたが、その途中で僕は再び睡眠状態に入ってしまったらしい。覚醒を感じ、テレビに目を向けると、そのニュース番組は終わろうとしていた。
僕はふと思い出す。「誕生日」という言葉。
布団から出ると、いつもそうしているように新聞受けのほうに向かった。もうすぐ8時。すでに新聞は来ているはずだ。
──なかった。
そこで僕には、ある記憶が甦った。先日、僕がきちんと確かめなかったために、新聞が来ていないと勘違いしてわざわざ事務所にまで電話してしまったことがあった。その日の新聞は量が多かったため、新聞受けに入りきらなかったのだ。外へ出て見てみれば、きちんと配達されていることは一目瞭然だった。
同じ過ちを繰り返さないために、僕は丹念に新聞受けを探った。あらゆる角度から、裏から表からしっかりと確認した。
だが、新聞は来ていなかった。
こうして僕の20歳の記念日は欠落した朝から始まったのだった。
大学への道の途中でいつも見掛ける犬がいる。近所の家の飼い犬なのだが、その犬について何か述べるとすると次の一言に尽きる。
生気が感じられない。
いつも「ぐだっ」としている。生きようとする力が全く感じられない。そこには何か絶望的な空気さえ漂っている。見た感じ、常に死と隣り合わせだ。
以前、僕はその犬の横を通り過ぎる際に一個のリンゴを与えたことがあった。
だが、ころころと一匹の犬のほうに転がっていくそのリンゴは、完全に無視された。興味を示されることは全くなかった。視界にすら入っていなかったのかもしれない。
その厭世的な態度と徹底したニヒリズム、生への渇望を感じさせない生き方に、僕は次第と親近感を覚えていった。毎日、通学途中に、彼の〈生きる姿勢〉を見ては、僕の内の何かが震えるのだった。
今日ももちろん彼はいた。やはり「ぐだっ」としていた。
ふと、僕はそんな彼に歩み寄ってみたくなった。
だらしなくうつ伏して、目も半開きの彼でも、リンゴではなく生身の生き物が近づいたら、何らかの反応を示すに違いない。少なくとも視線を向けることぐらいはするだろう。
僕は道の傍らにいる彼にかすめるように近づいていった。そして、ある程度まで距離が詰まったときだ。
逆鱗に触れたのだろうか。
それまでアメーバのようにだらだらしていたそれは突然に豹変し、僕に噛みつこうとするとともに敵意を剥き出しにして吠えた。
ものすごく吠えた。本当にけたたましく吠えた。
かなり慌てた。よけたから良かったものの、もう少しで噛みつかれるところだった。歩調を乱しつつも通り過ぎて行く僕の背に、その犬はずっと吠え立てていた。
それに触発されてか、向かい側の家の大型犬まで僕に吠えた。僕は自分が小さくなっていくのを感じた。
二頭の犬の咆哮に見送られて学校へと向かいながら、ふと思い出す。
「誕生日」
20歳の誕生日といえども、そんなものなのだろう。むしろ劇的に大人になる者のほうが少ないはずだ。
僕は犬に厳しく威嚇されながら20歳を迎えた。だが、世界のどこかにはライオンに噛み付かれながら成人するような者もいるに違いない。