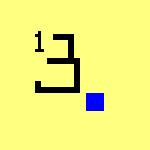恋人とショッピングモールをふらふらしていたのである。
ここで断っておかなければならないのは、ここで出てきた恋人という事象は全く重要ではないということだ。人はロマンスの渦中にあると大抵は思考がくだらなくなるのであり、「今日ゎ、彼氏と水族館に行ってきました! お前、手ぇ冷たいなぁとか言って、ずっと握っててくれて、ちょー嬉しかった〜☆ずっとラブ×2でいようね♪」などという惨憺たる報告になりがちなのである。そんな日記、公開するなと言いたい。ゲーテの『若きウェルテルの悩み』は、そのくだらなさが頂点に達しているという意味で傑作なのである。
少なくともこの文章に関しては、買い物をしていた相手が、友人でも従兄弟でもその辺のおっさんでも話は成立するのだが、たまたまその時は恋人と一緒だったというだけのことだ。「のろけ話」という先入観を持たれないための弁明であり、物語はそこから始まる。
それは「のろけ話」とは程遠い、大人の物語だ。
コーヒーが飲みたくなったのだった。突然、温かいコーヒーを口にする自分の姿が頭に浮かんだのだ。
「コーヒー飲みたい」と言うと、我々はスターバックスへ向かった。
彼女はスターバックスを好んでいるが、僕はそれに全く興味がない。彼女曰く、ドトールやタリーズなんかよりもスタバのコーヒーが飛びぬけて美味しいんだそうだが、僕にとってコーヒーはコーヒーであり、スタバだろうがスーパーの特売品だろうが同じものに感じられるのである。まして、なんとかマキアートだの、なんとかフラペチーノだのなんて、さっぱりわけがわからない。僕の中のコーヒーのバリエーションは、コーヒーとカフェオレとカプチーノのみだ。コーヒーにも、アメリカンとブレンドというものがあるらしいが、これらの違いもよくわからないので、注文の際は、ホットかアイスかのみを告げることにしている。「ホットコーヒーをひとつください」ということである。
ホットコーヒーが飲みたかったのである。程よく調光された店内で、コーヒーを啜りながら身体を温め、午後のひと時を過ごすはずだった。彼女はカフェラテを頼んだのだと思う。コーヒーについて興味の薄い者は、その記憶も曖昧であり、従って「だと思う」としか表現できないのだ。しかしながら、それに次いで自分が発した言葉ははっきりと覚えている。
「エスプレッソ」
なぜか、エスプレッソを注文してしまったのだった。メニューを眺めていたら目に付いたので、口にしてしまった。エスプレッソにはサイズが二種類あったのだが、とりあえず初心者は安いほうを頼んでおけば間違いないと思い、メニューを見ながら「soloで」と言った。彼女が驚きと半笑いの表情でこちらを見続けているかと思えば、オーダーを受けた店員もなぜか顔が笑っていた。僕は彼女に言った。「エスプレッソって何?」
ものすごく濃いものだということは、かつてから耳にしていた。そしてそれが大人の飲み物だということも知っていた。渡されたエスプレッソは、人を馬鹿にしているのかというほど小さなカップに、ほんの少量だけ注がれていた。つまり、それほど濃度が高いということだ。
いまだかつて、スターバックスでエスプレッソを飲んでいる者を僕は見たことがない。そのとき僕がエスプレッソを注文することで、大人としての優越感に浸ることができたとしても、そもそもホットコーヒーを目的としていたわけであり、なぜエスプレッソを飲む羽目になったのかはわからないのだった。
席につき、まず僕は彼女に小声で高らかに宣言した。
「俺、エスプレッソが何なのかさっぱりわからないし、そもそも今日初めて注文したんだけど、『スタバに来たらいつもエスプレッソなんですよ』ってフリして飲むから」
かの格調高いエスプレッソなのである。注文したはいいが、苦くて飲めませんでした、なんてことは恥ずかしいし愚の骨頂である。従って、「soloで」とオーダーした際も、ビル・エヴァンスのピアノソロのような気品と優美さを備えて、そう告げたつもりだ。
飲んでみたら、当然ながら苦かった。喉が渇いたのでコーヒーを飲みにきたはずなのだが、余計に喉が乾いていくようだった。エスプレッソを前に、僕は饒舌になっていた。
「コーヒー好きはやっぱりエスプレッソを飲まないようじゃ話にならないよね。エスプレッソ抜きでコーヒーを語るなんて、ふじりんごを食べないでりんごを語るようなもんだよ」
何を言っても言葉が空回るのがわかった。彼女も、僕のエスプレッソをひと口すすったが、険しい表情をして無言でカップを元の位置に戻した。
「そもそもコーヒーってのは、エスプレッソが基本なんだよ。だから、エスプレッソを優雅に嗜めないようじゃ、全てのコーヒーに失礼だよね。エスプレッソを理解できないなんて、とんこつラーメンのないラーメン屋みたいなものだよ」
確かに最初こそ苦いだけだったが、口にするたび、コーヒー豆の深い香りが広がりをみせるのがわかった。これは普通では味わえない感覚であり、増して、カフェラテなどでは言語道断である。ただ、喉は渇いた。ただでさえ喉が渇いていたのに、エスプレッソが追い討ちをかける形となっていた。
「コロンブスがコーヒー豆をヨーロッパに持ち帰って、最初に作られたのがエスプレッソの原型なんだ。だから、文明人が初めて飲んだコーヒーがエスプレッソだったってわけ。エスプレッソを味わうことで、コーヒーの歴史をも味わえるなんて最高の気分だね」
そのような史実があるのかどうか知らないが、とにかく饒舌になりたい気分なのだった。なぜなら、エスプレッソを嗜んでいるからである。彼女があくびをしたので、エスプレッソを勧めたが、頑なに拒否された。
「エスプレッソは数あれど、スタバのエスプレッソは香り高くて、一度味わったらなかなか抜け出せないな。それは厳選された豆と卓越した技術によって成しえたものなんだろうね。エスプレッソを味わってみれば、その店のコーヒーの全てがわかると言われているんだ。つまり、今、味わっているこのエスプレッソっていうのは、最高の技術が注ぎ込まれた傑作ってわけなんだ」
そうやって、僕は時間をかけてエスプレッソを飲み干した。当然ながら、苦味のせいで時間がかかったのではなく、香りと味わいとそれらの余韻を楽しんでいたため、時間が費やされたのである。店内でエスプレッソを飲んでいる者は僕だけだったが、なぜみんなエスプレッソを注文しないのか不思議だった。
エスプレッソは飲み物ではなく、思想である。エスプレッソはコーヒーではなく、哲学である。エスプレッソは存在ではなく、方法である。エスプレッソはリアリティではなく、イマジネーションである。エスプレッソは物理ではなく、ファンタジーである。エスプレッソはエスプレッソでしかなく、且つ、それ以上である。
「今日というこの瞬間にエスプレッソに立ち会えて、本当に良かったと思っているんだ。もう二度と飲むことはないにしろ、この出会いはとても重要なことだったよ。エスプレッソを知らない人生なんて、音楽の入っていないiPodみたいなものだね」
スターバックスを出て、僕は彼女に「トイレに行ってくる」と告げてその場を離れ、ジュースを買ってものすごい勢いで飲んだ。饒舌になりすぎて、喉がからからだったのだ。つまり、それがエスプレッソの力である。