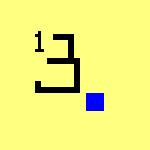芥川也寸志が著した『音楽の基礎』にこうあるのを見つけた。
「リズムを喪失した音楽は死ぬ」
死んでいるのである。親しい友人や家族が嗚咽し、受け入れられない別れを突き付け、身体を燃やされ、墓の中に埋葬されるという、あれである。なんという鮮烈な擬人であろうか。「リズムを喪失した音楽は、もはや音楽ではなくなる」と、そう言っても良かったのであろうが、著者は「死ぬ」という表現を選んだのである。
そこには、強烈なインパクトと衝撃が内在している。「死」とは、我々の日常生活においてはタブー視されている趣きも感じられるが、使い方如何によっては、我々を黄泉の国とは違った異次元にいざなう効果をも持っている。
例えば、フジテレビの斉藤舞子アナウンサーがこんなことを言っていた。
「フットサルの練習をしすぎて、右足の親指の爪が死んでいる」
どんな状態だ。しかし、我々にそれを知る術はない。なぜなら、彼女の右足の親指の爪を見ることはできないからである。
もしかしたら、痛みを感じないという意味の「死んでいる」かもしれないし、死と同然の様相を呈しているという意味かもしれない。爪が剥がれ落ちてしまい、存在しなくなってしまったという意味なのかもしれないが、それはわからない。
「爪が死んでいる」などというエキセントリックな表現の前には、我々はただ立ち尽くすか、笑うしかない。
「死んでいる」という言葉で、まず初めに連想するのは次のものではないだろうか。
「お前はもう死んでいる」
あいにく僕は『北斗の拳』については全くの無知ではあるが、この名言くらいは知っている。主人公の人間離れした人物が、相手のツボ的な場所を突き、その台詞を吐くと、相手は意味不明な言語を断末魔として自らの内部から崩壊していくのだ。
ここで注目すべきはその台詞を聞いている人物は「死んでいる」と宣告されているにも関わらず、その言葉を聞くことができている、すなわち、生きているという事実だ。それが証拠に、そう宣告された相手が「えっ?」みたいな表情をみせるのを僕は目撃している。「死んでいる」には、時間的パラドックスを生じさせる効力をも持っていたのである。
「死んでいる」には、社会的タブーを超えて様々な効力があることがわかった。それは「荼毘に付す」などといったものとは、別の次元に向かっている働きだ。
「昨日までの俺は、死んでいた」
そう言って新たな一日を踏み出すことができたなら、どんなに素晴らしいことだろう。