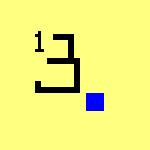咳の歴史とその効用
咳の起源
咳は、人間がまだ野生動物だった頃の「鳴き声」の名残りであると言われている。
一匹が何だか変な鳴き声をするのを聞けば、「ああ、あいつは風邪なんだな」とわかるわけである。もちろん、その変な鳴き声をした当事者も、「自分は風邪だぞ」ということを周囲にアピールし、その情報を伝達しようとしているのだ。
進化の過程で我々は「言葉」を発明し、次第に「鳴き声」は不要になっていった。しかしながら、咳だけは残ったのである。あらゆる「鳴き声」を放棄しておきながら、咳だけは、現在でも「風邪だぞ」を意味する伝達手段として維持し続け得ている。つまり、我々は誰かが咳をすれば、「あいつ、風邪だな」と必ず思うことになっているが、それは、進化の蓄積によって培った本能的なものだということである。すなわち、我々が風邪に罹った際に咳をしてしまうのは、のどが痛いとか、たんが絡むとか、ウイルスを体内から排除しようとする働きであるとかの理由の前に、それが本能的な伝達手段であるからなのだ。
咳という漢字について
「咳」という漢字は、「赤子が笑う様子」を意味するらしいが、文化人類学的見地によれば、「人は、人として生まれるのではなく、人として育てられる」のであるから、育成途上のその赤子は「まだ人間ではない」のであり、従って、「咳=動物」の構図を描くことができ、咳が我々における動物時代の名残りであることを導き出す一つの手掛かりになり得る。
加えて、我々は笑いすぎると呼吸のリズムが混乱し、むせて、風邪でもないのに咳が出る。当然に、成長して社会的分別を身に付けた者よりも、赤子のほうが無邪気であり、よく笑う。従って、笑いすぎた末の咳も赤子のほうが圧倒的に観察されるのだ。この様子を見た者が、それを「咳」と定義付けたのであり、「そういえば、風邪ひいたときに出るやつもなんか似てるな」と後世の誰かが気付き、現在の意味の「咳」が完成したのであろう。
人間の文化においては、理性が本能に先行するのである。
咳の効果
現在の咳の効果も、野生動物時代の咳の効果も、基本的には同様である。
すなわち、誰かが「ゲホッ」と咳をすれば、周囲の者は「ああ、風邪なんだな」と思うと共に、「大丈夫か」と気に掛けてくる。野生動物には言語がないが、傍に寄り添うくらいのことはするだろう。いずれにしても、その者に対する心配を発動せしむることができるわけである。このコミュニケーションによって、その共同体の関係性はより強固なものになる。
より過激で常軌を逸した咳(「ゲーッホッ、ゲホッ、ゴホッ、ゴホホッ、ゲホッゴホッ、ゴホーッ、ゲホッ、ゴホッ、カーーーーッ、ゲホッ、ゴホッ、ゲホホッ、ゴホッ、ゴホッ、ゴホゴホッ、ゲホッ」が断続的に続く)をした場合、周囲の者は「あいつ、やばいんじゃないか」と思い、「病院行ってこいよ」と声を掛けてくる。この場合の「病院行ってこいよ」は、心配であると共に警戒である。つまり、「病院に行って治してきたほうがいいよ、みんなに伝染するから。もしそれが重病で、こっちに伝染したらどうしてくれるんだ」ということだ。野生動物の場合は、それがウイルスのせいであることを知らないので、そのまま寄り添うことはするが、やはり、いくばくかの警戒心は生まれることとなる。「大変なことになっているが、なんだかわからないけど、近寄らないほうがいいんじゃないか」ということだ。こうして、その咳の当事者は群れから距離を置かれることとなる。それが、彼らなりの「治療」ということになっているのだ。無菌室に隔離するようなものだ。
勘違いしてはいけないのは、このような周囲の行動は、彼らの独立した判断のみにおいて発動されるものではないということである。先にも述べたとおり、咳というのは情報の伝達手段なのだ。すなわち、咳が規模において割と小さいときには、「ちょっと誰か心配してくれよ」ということを周囲に向かって暗にほのめかしているのであり、その咳を聞き取った者はそれを感じ取り、しかるべくしてその咳の当人を心配するのだ。同様にして、過激で常軌を逸した咳の場合は、「なるべく離れろ。伝染するぞ」ということを咳によって表現している。よって、周囲の者たちも、しかるべくして「病院に行けよ」と突き放してみたり、その共同体から隔離しようとするのである。
概ね我々の意識内で、小さい咳をしている者に対しては過剰に心配したくなるが、やたらと大きな咳を連続的にしている者に対しては、発動される心配を嫌悪感が上回り、「うるさいな」としか感じなくなってしまうのはそのためだ。咳自体が、その咳をしている当人を隔離させるべく、周囲の者に作用するからである。
咳をしている当人にその意識はなくても、それは進化の過程で培った本能なのであり、その本能が咳をする側と咳を聞く側とに共有されているために、こういったことが起こり得るのである。
病気の証明としての咳
咳の作用は、基本的には上記の通り、「心配」と「警戒」であるが、人間が言葉によってコミュニケーションを図るようになってからは、もう一つの働きが重要視されるようになった。
すなわち、「病気の証明」である。
例えば、ある者が「風邪ひいたよ」と言ったとしても、その者が実際に風邪をひいているかどうかは、その当人以外にはわからない。言語とは、ある事象を主観的に表現することができるだけであり、その真偽にまで責任を持つものではないのだ。このような言語の陥穽を達者に操ることにより、人間は嘘をつき、人を騙し、詐欺に陥れるわけだが、それを経験上知っている我々は、「風邪ひいたよ」とだけ告げられても、何だかしっくり来ないのである。
そこで、咳の出番だ。咳に言葉は必要ない。
咳が出そうになったら、その流れに逆らうことなく、それをそのまま放出すればいい。
「ゲホッ」
たったこれだけで、自分が風邪をひいていることを、ダイレクトに、確実に伝達することができるのである。すなわち、自分が風邪をひいていることを証明する手段の一つとなるのだ。
現代の先進国においては「仮病の時代」が到来しており、学校を欠席するにしても、会社を欠勤するにしても、自らに課せられたあらゆる義務・責任を放棄するにしても、その理由を「風邪だから」と告げられたとして、「本当に風邪である」ことによるものか、それとも「仮病を用いた」ことによるものか、それらが混在し、真偽を判別することが難しくなっているのが実情なのである。すなわち、仮病の台頭により、真性の風邪における信憑性が危うくなっているのだ。
咳がそれを解決する。劇作家の別役実氏によれば、「仮病としての《風邪》は表現に際してかなり高度な技術を要する。(略)自然に「せき」をしてみせたりするのは、やってみればわかるが、意外に難しいものなのだ」ということだが、従って、これに基づけば、咳によって、自らが風邪であることの真実性を容易に伝達することができ、仮病に対する風邪のアイデンティティーを確立することができるということである。「高度な技術を要する」のだから、練習を積み重ねることによって、仮病としての風邪における咳を身に付けることも実際には可能なのではあるが、その向上心を仮病に注ぎ込まんとする者は、途中で、自らが放棄しようとしていた労務にその努力を支払ったほうが合理的であることに気付くだろう。
もちろん、自らが風邪であることを証明するために、体温計によって平熱ではないことを示したり、青ざめた顔を見せるという手段もあるが、咳の前には敵わない。電話越しに自分が風邪であることを証明するためには、咳以外の手段は用を成さないのである。当然に、電話を通じては青ざめた顔を見せることはできないし、熱が出ていることを力説しても、言葉が上滑りするだけなのだ。それに対して、咳はダイレクトに相手の本能に訴えかけるのである。
まとめ
咳は、最も原始的にして、最も効果的な伝達手段である。
人間がここまで高度に進化してきたにも関わらず、自らが何らかの病気であることを伝達するために、咳などというものをいまだに用いているということは、我々にとってウイルスがいかに脅威であり続けてきたかを示している。
風邪には気を付けましょう。