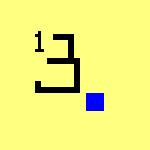スポーツと「声」の関係について
カーリングにおける掛け声
トリノオリンピックの女子カーリングを見ていて気付いたのは、自分のチームの「取っ手のついたなんか重そうなやつ」(「ストーン」)が放たれて、それが遠くにある二重サークル(「ハウス」)に向かって氷上を移動している間、選手たちが何やら叫んでいるということである。しかも、何を言っているのかわからない声があがっているのだ。
私は日本人であり、日本語を殆ど理解しているつもりだが、それでも日本選手が何を叫んでいるのかわからない場面が多々あった。「ウォー」とか「エー」とか、そんな感じだ。「ストーン」を放った選手も、ブラシで氷を磨く選手たちも、たぶんもう一人の選手も、一様に大声を出しているのである。その声は、戦況が緊張感のあるものになるに従って大きくなっていった。
もちろん、それがある種のサインや専門用語でないとも限らない。もしそうだとしたら、実践的なカーリングについて無知な私にとって、何が何だかわからないのも当然なのである(聞くところによると、「ウォー」は「そのまま」の意だそうだが、他はわからない)。麻雀について無知な者が「ポン」だとか「タンヤオ」だとか「イーシャンテン」だとか聞かされても、全く理解できないのと同様である。
ただ、それが「サイン」あるいは「専門用語」による「指示」であり選手間の「コミュニケーション」であるとしても、そう判断するには、女子イタリア選手の声は感情的に過ぎた。カーリングは極めて冷静さが要求される競技であり、指示を出す際に感情的になってはいけないのである。「ストーン」を放った瞬間にそれを行った彼女自身が「タァァァァーーーーーーー!」とわめいているようでは、それを「指示」とみなすにはあまりにも頼りない。
それが「指示」であることを否定しているのではない。そこに、「指示」あるいは選手間の「コミュニケーション」以上の何かが存在しているらしいということを言いたいのである。
そこで、次のような説が浮かび上がる。
――スポーツは「声」である。
野球部での経験からわかったこと
中学時代、私は野球部に所属していたが、入部してまずやらされることは、先輩たちがキャッチボールをしている後方で、球拾いをしながら、声を出すことである。
この際、「球拾い」よりも「声出し」に力点が置かれていることは明白だ。その時点で、「ボールの拾い方」や「ボールの投げ方」などは何一つ教わらなかったものの、「声の出し方」における教育は丹念に受けたからである。さらには、我々新入部員が、だめなフォームで見当違いなところにボールを返したとしても、彼らにこっそり舌打ちされるだけだが、声が出ていないと、大々的に厳しく叱られるのだ。
加えて、「球拾い」などはいなくてもキャッチボールは正常に機能するのであり、その「球拾い」は、「声出し」の殆ど「ついで」と言っても差し支えないだろう。先輩たちは少なくともその時点で野球を1年以上は経験しているので、キャッチボールにおいて失敗することはまずない。従って、「球拾い」の新入部員は、大抵は暇なのであり、「声出し」に力を注がざるを得ないということになっているのだ。
これは、「スポーツとしての」野球を新入部員に教えるための戦略に違いない。スポーツは「声」であるので、野球の基礎であるところのキャッチボールなどはそっちのけで、まず「声出し」をさせるのである。スポーツとは何たるかをまず教え、それを身体に馴染ませ、頭に叩き込ませるのある。
そして、その「スポーツ」の基礎が充分に理解でき、体に染み付いたとみなされた時、初めて我々は「野球」に触れることができる。すなわち、キャッチボールをさせてもらえるのだ。
従って、我々の野球部にあっては、基本として「さーこいー」という謎の掛け声を出すことになっていたが、「声を出し」てさえいれば、その内容は何でも良かったに違いない。ただ、みんながみんなそれぞれにわめいていてはあまりにも混沌としすぎ、チームとしての結束が促されないであろうということで、基本を「さーこいー」として設定し、その他の応用の部分においては個々人に委ねるということになったのだろう。
すなわち、団体競技においては、自らのチームが設定した「声」を出すことにより、結束が強まるという効果があるのだ。当然に、その「声」が「指示」あるいは「コミュニケーション」の働きをするものであったとしても、「指示」あるいは「コミュニケーション」をしながら、結束が強まっているのである。
団体競技において最も重要なのは、言うまでもなく、個々人の能力の高さではなくチームワークなのであり、「声」によってそのチームワークの向上を画策しているのだ。
意識付けとしての「声」
ただ、「声」にはそれ以上の重要な働きがあると私は考える。
例えば、カーリングにおいて、「ストーン」を投げる選手のことを考えてもらいたい。選手は「ストーン」を片手に、片足で勢いをつけ、それを戦略通りの場所に向けて放つ。そこまではいい。
「ストーン」がその選手の手から離れ、「ハウス」の方に向かっていく。その時、「ブラシ」で氷上を磨く選手たちは、「ストーン」と併走しながら、「ストーン」の動きとターゲットの場所とをよく見比べ、「ブラシ」の扱いについてよく考え、必要とあらば「ブラシ」を氷上で忙しく動かすのだが、一方、「ストーン」を放った選手は手持ち無沙汰なのである。「ストーン」を放ったはいいが、そこから当人がすべきことは、遠ざかる「ストーン」の行方を見守るくらいしかない。
つまり、暇なのだ。「ストーン」をぼんやりと見つめながら、彼/彼女は思う。
「私は何をしているのだろう」
そこで、「声」を出すのである。「あー」でも「どりゃー」でも何でもいいのだが、TPOを考慮して、できればカーリングという競技に沿ったものがいいだろう。それを日常では出さないような大声で叫ぶのだ。
すると、はっと我に返る。
「そうだった。私はスポーツをしているのだった」
これである。すなわち、「声」は、スポーツをしている状態を忘れがちになる競技者において、スポーツをしていることを思い出させ、緊張感を持続させる役割を果たすものであると言えよう。
氷上をブラシで磨いている選手は、見るからに「ストーン」の前方をブラシで磨いているのであり、スポーツをしていることが明白だが、それでも「声」を出しているのは、「ストーン」を投げた選手に対して「スポーツをしているのだということを忘れるなよ」と示唆すると共に、自らについても向上心を発揮し、「さらにスポーツをしている」状態へと押し上げようとしているためである。
野球でも同様である、レフトの位置に立ってはいるが、自分がそこで何をしているのかわからない。ボールがひっきりなしに飛んでくるわけでもないし、常に動き回らなければいけないわけでもない。そこで、「声」を出す。
すると、「そうだ、俺はスポーツをしており、レフトの守備をしているんだ」と全てを思い出すというわけだ。あるいは、チームメイトが「声」を張り上げているのを聞いても、同様の効果が得られる。
我々の野球部においては、ベンチにいても「声」を出すことになっており、それは他の学校も同様だったようだが、これもスポーツをしていることを忘れないためであると言える。油断すると我々は、つい「何でこんなところに座っているんだ」と思いがちであり、そのまま帰宅してしまいかねないので、「声」を出すことによってそれを回避しようと試みているのである。
プロ野球においては、中学野球や高校野球ほどにはやかましく「声」を出していないようだが、それは、彼らは「声」を出さずともスポーツをしているということを忘れない領域にまで達しているからである。彼らは、そういう意味で「プロ」なのであり、スポーツにおける一つの極致である。
もしくは、ハンマー投げの選手からわかること
あるいは、当初は「スポーツをしていることを忘れないため」の「声」だったが、それを続けていると、声を出すこと自体に意味を見出すようになる。これこそが、スポーツのもう一つの完成型である。
その最たる例が、いつかのオリンピックのハンマー投げの選手だ。
ウクライナの男性選手だったと思うが、彼は、ハンマーを投げる前に気合いを入れすぎてタイムオーバーになったのだった。時間を忘れるほどの気合いだが、それがすごかった。全身全霊をかけ、叫びまくりだ。
彼は、「スポーツ」をすることに集中しすぎたが故に、「ハンマー投げ」を遂行することなく時間切れで失格になった。だが、「スポーツ」というものの本質を捉えているならば、彼は満足だったに違いない。ハンマーは投げられなかったが、ものすごい声は出せたのだ。「スポーツ」をするという点においては、人の何倍もフィールド上で達成したのである。
もし彼に、「メダルを獲りたい」などという邪な考えがあったとすれば、かなり残念がっただろうが、純粋に「スポーツをしたい」という意志によってオリンピックに出場したのだったら、晴れ晴れとした心境でその場を去ったはずなのである。
まとめ
スポーツにおける「声」は、各選手をして「スポーツをしている」状態たらしめるために発動される。そして、それが殆ど完成に近づくと、上記のハンマー投げの選手のように、「声」を出すためにスポーツをするようになる。つまり、「声」と「スポーツ」は、相互に作用し合う密接な関係のもとに存在していると言える。
スポーツは「声」である。
あるいは、「声」はスポーツである。
スポーツをする際は、とりあえず声を出しておけばなんとかなる。そうすることによって、紛れもなくスポーツをすることができるのである。