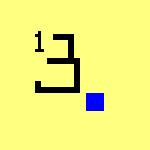イアニス・クセナキス『ペリセポリス』
『ペルセポリス』を聴きながら眠りにつくのが、最近気に入っている。
この曲は、ギリシャの現代作曲家イアニス・クセナキス(Iannis Xenakis, 1922-2001)によって1971年に作られた電子音楽で、彼の最高傑作であるばかりか、20世紀の遺産であり、今でも音響系アーティストの間ではバイブルとして扱われているものであるらしいが、この作品に対して何か言うことがあるとすれば、「わけがわからない」ということだ。音楽という位置付けにありながらメロディーなどというものは皆無であり、金属的な高音が無機質に鳴らされる中、得体の知れない轟音がひたすら暴れている。その轟音は、世界の終わりのような音だ。空爆のようであり、ジェットエンジンのようであり、水道管の破裂のようでもある。そんな脈略のない音の塊が約50分に渡って吐き出される。
クセナキスという人は作曲家でありながら数学者でもあり、彼の作品は数学によって作曲されていたようだ。
数学には感情がない。「三人寄れば文殊の知恵」などという概念は数学にはなく、それはただの「3」でしかない。それ以上でも、それ以下でもない。あるいは、ある者が非常に大切にしていたものをなくしたとしたとて、それは数字上では「-1」でしかないのだ。
しかし、音楽は違う。音楽の起源については、動物の鳴き声の模倣だとか、話し言葉の抑揚から発生したとか、「死」を超越するための祈りから生まれたとか、様々な見解があるが、いずれについても共通していることは、それが感情に基づいているということだ。
すなわち、数学によって作られたクセナキスの作品に、何らかの感情を読み取ることは全くもって不可能だ。それは『ペルセポリス』も然りである。僕が思うに、これは音楽ではない。
何も考えたくないと思うことが往々にしてある。そんなときにはただ何もしないで音楽にでも耳を傾けていることにより、気分が良くなることもあるが、そんなことでは気持ちが癒えない時もあるものだ。そもそも、この世界で生きる我々にとって、世界は人の心で構成されているといって間違いない。例えば、我々の抱える悩みなどというものには、全て人間が関係しており、その人間を突き動かすのは、他でもない、理性の名のもとの感情だ。そして、音楽もまた感情である。何らかの苦悩を抱える者にとって、それが音楽によって癒される場合もあるが、そうでない、もっと根本的で深刻な、想像を絶するような問題を抱える者には、音楽は無用なのかもしれない。音楽に込められた心が、必ずしも人間を癒すとは限らないからだ。
そんな時の『ペルセポリス』だ。これを聴く者の態度は、限りなく無心に近い。この曲自体が無感情なのだから、それを受け取る側も同じ姿勢になるのは当然といえば当然のことだ。あるいは、理解不能な凄まじい音の嵐の前で、思考がはたらく余地がない、といった効果なのかもしれない。
ここに究極の逃避がある。共感による癒しでも、諦めでもない、無心による現実から逃避だ。そのためには、無音空間では足りない。得体の知れぬ轟音に身を浸すことによって、人は無心になり得るのだ。無音には、人の思考を留める力などない。それは、静かな部屋の中で一人でじっとしていると、なんだか死にたくなることからも明らかだ。少なくとも、無心状態にあれば、そういったネガティブな発想は心に現れない。つまり、ここにおける逃避とは、ポジティブでもなければネガティブな方向でもなく、現在地点を全く動かずに引き起こすことのできる作用だ。
クセナキスという人がどういう意図をもってこの曲を作ったのかはわからないが、それが僕から見た『ペルセポリス』の側面だ。
Iannis Xenakis
WDR Sinfonieorchester Ensemble Ars Nova de I'ORTF Orchestre Philhrmonique de I'ORTF